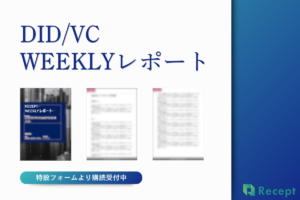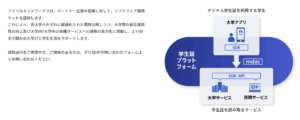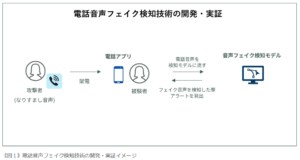DID/VCがビジネスとして成立しない5の理由

DID/VC(Decentralized Identifier / Verifiable Credential)という技術があります。弊社はその技術を専門として1年ほど事業を行ってきました。
この技術にフォーカスした事業のうち、持続的な利益を生み出している事例はグローバルでもほとんど無いのではないかと思います。
本記事ではその理由を列挙していきます。
①ただの規格問題
この技術を単純化すると、VCは「データの記述方式を定めるルール」でDIDは「VCが紐づく先の識別子+鍵の情報」です。(DID/VCの技術説明は他文献に譲ります。)
UIレイヤーでユーザーが技術の素晴らしさを実感できるような技術ではないため、ピュアに使ってもどうしても提供価値が伝わりづらいです。
②日本における「ボーダレス実現」の必要性の薄さ
先述の通りDID/VCはルール≒標準仕様です。
標準仕様が固まるとビジネスレイヤーで嬉しいこともあります。例えば画像データはpngやjpgといった標準仕様があることで異なるアプリケーション間でも互換性がありますし、メール授受のプロセスなんかも同様です。
VCはデジタル証明書の規格として採用されたりするのですが、そのデジタル証明書が流通するスコープが日本に閉じていると「これまでデータ規格が異なることで手間暇かかっていたプロセスが効率化されます」という売り出し方は厳しくなります。

③能動的採用シーンの少なさ
技術がある程度の存在感をもって新規事業に組み込まれる際、ビジネスオーナー目線で採用動機は以下二つに大別されます。
- レギュレーションや業界動向的にその技術を採用せざるを得ない
- その技術の特性・特徴が検討中のビジネスと相性がいい
弊社では前者を「受動的採用」、後者を「能動的採用」と呼んでいます。
前者は相対的に「規制変化や行政案件など自社でコントロールしづらい変数」に左右されがちで、ビジネスをスケールさせたい場合には往々にしてネガティブに作用します。
④予備枠予算の下りづらさ
多くの会社では「あらかじめ確保された年度予算」と「年度内で使途を流動的に決められる予備枠予算」があります。
後者予算が取れるタイプのサービスは前者のそれと比べて成長スピードや受注機会の観点で優れています。
残念ながらDID/VCはその枠には採用されづらい技術です。(直近ではAIやセキュリティといった領域が後者で強いイメージ)
⑤SSIと資本主義社会の不一致
SSI(Self sovereign identity)という考え方があります。これは「自己主権型アイデンティティ」と訳され、「個人のアイデンティティ情報は本人が管理できるべき」という概念・ムーブメントです。
DID/VCもSSI文脈の中で語られることがあります。(情報銀行やWeb3といった取り組み・領域を想像される方もいらっしゃるかもしれません)
SSIは資本主義の原理と反発しがちです。例えば「アイデンティティ情報を企業が囲い込む」のは「資本主義社会において利潤を追い求めることが課された企業にとっては当たり前のこと」であり、そこにメスを入れることは利潤追求と矛盾が生じます。

そんなこと言いつつDID/VCベンチャーやってます
こんなこと書いていながら、DID/VCのポテンシャルとビジネス可能性を疑ったことは事業を始めてから一度もありません。
経営戦略や競争戦略についてあまりべらべら喋るわけにもいかないですが、心構えとして「難しい技術を簡単に売る」ことを意識しています。
「難しい技術を売る」は、「(特筆すべき経歴や後ろ盾をもたない若い経営者が)どの領域でベンチャー企業を立てるか」というマクロな観点で弊社を特徴づけています。AIや業務効率化サービスは明らかに需要がありビジネスチャンスも広がっていますが、その分参入者が多く熾烈な競争がおこります。一方でDID/VCはまだ未開拓な領域です(そして人生の一部をかける十分なポテンシャルがある!)。
「簡単に売る」は、もっとミクロな視点で「業界内でReceptをどう位置づけるか」の話になります。弊社が参入した2024年時点でDID/VC基盤を提供する事業者は多数いらっしゃったので、弊社を際立たせるためにもプロダクト紹介・ピッチ・日々の発信・製品価格などあらゆるシーンでの「分かりやすさ」を大事にしています。
★特別なお知らせ★
デジタルアイデンティティの最新トレンドを毎週お届け!
業界の最前線をまとめた「DID/VC Weeklyレポート」を毎週無料で配信中です。こちらから簡単に登録できますので、ぜひ情報収集や新規事業のタネ探しにご活用ください。