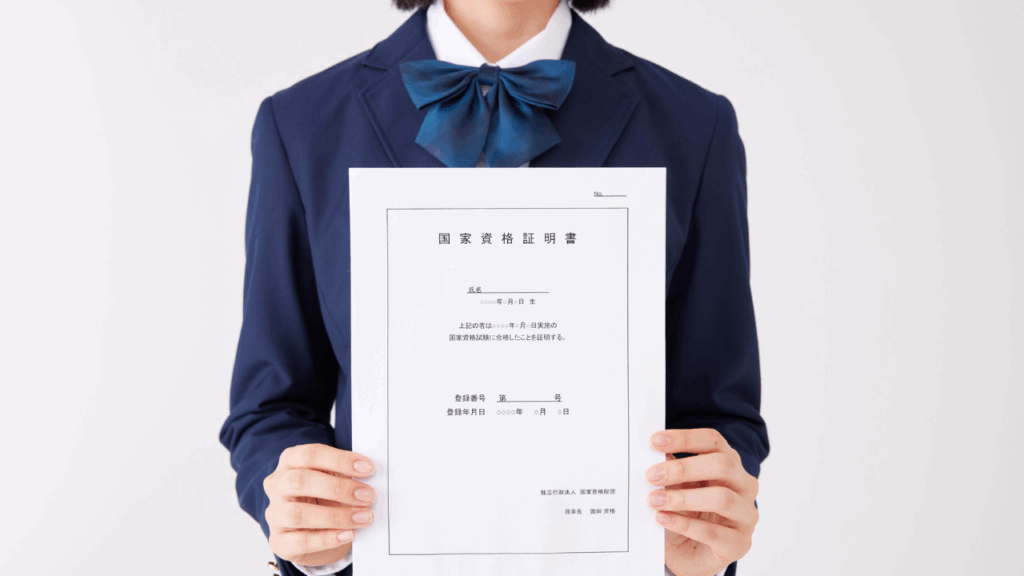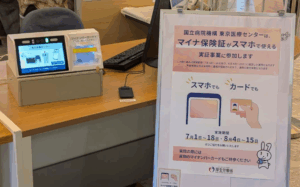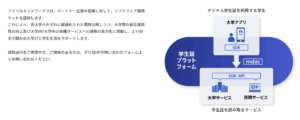オープンバッジv3でVerifiable Credentialsになった──理想と現実
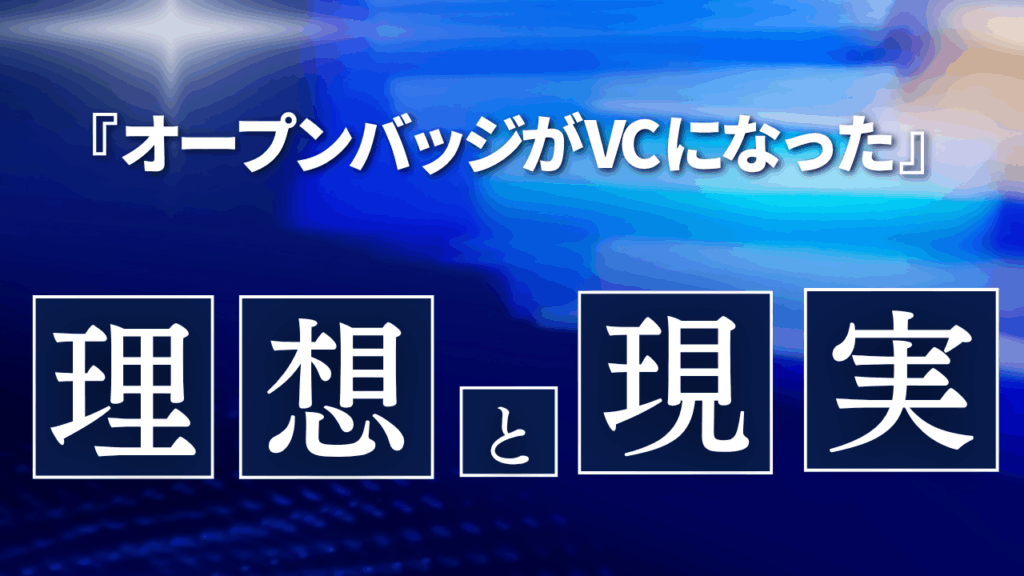
Open Badges v3への移行と期待感
Open Badges(OB)は、1EdTech(旧IMS Global)が策定する学習・資格のデジタル証明書仕様です。
Open Badges v3.0 Specification が公開され、W3C Verifiable Credentials(VC)Data Model をベースにした新しいフォーマットが採用されました。
(筆者の負担を減らすため、オープンバッジv3.0はOB v3, Verifiable CredentialsはVCと記載いたします)
この動きは教育分野の標準化だけでなく、越境的な証明・検証の相互運用性を高めるきっかけになると考られます。DID/VCの普及を願うポジショントークとして、OBというこれまで身近なシーンでも発行されていたクレデンシャルがVCになる、という記事を投稿しています。
オープンバッジとは? 【最新規格3.0についても解説】
デジタル証明書や学習履歴を示す手段として注目される「オープンバッジ(Open Badge)」。最近では「オープンバッジ3.0」という新たな規格も登場しています。 本記事では、…
しかし仕様書を読むと、「VCという形をしているが、プロトコルや運用は従来型」という現実も浮かび上がってきます。本記事はOB v3とVCについて話すうえでつけておくべき前提認識という観点で、期待していることと現実について記載いたします。
OBがVCになったことで広がるユースケース
国境を越えた教育・スキル認定の標準化
OB v3は、W3C VC Data Modelを採用し、教育から職業訓練まで広範な領域で相互運用性を高めます。
各国間でOBを用いたデジタル証明書の互換性向上が期待されており、下記のような事例や活用例がございます。
国際的取り組みの事例
- Purdue大学(米国)をはじめ、多地域・多組織でOBが利用されており、国際的な受容基盤の形成に向けて活用がされている。
- Credlyというオープンバッジ発行サービスでは、特にIT系のサービスの資格(例えばAWSの認定資格など)を所有することを表明するツールとして利用。
- EUではEuropassやEuropean Digital Credentials for Learning(EDC)といった取り組みが進み、VCやバッジを活用した学習成果証明の相互承認の実証が進んでいる。
実務的な活用例
- デジタルウォレット統合
学習者がOB v3を政府発行IDや他の資格証と共にウォレットに保持し、国境を越えて提示可能。 - 専門職資格のオンライン提示
医療や法律分野で、資格証明をオンラインで安全に提示・検証。 - 採用プロセスへの組み込み
求職者が提示するバッジを企業側が即座に検証し、採用判断に活用。 - 業界承認(エンドースメント)
発行元以外の第三者がバッジを承認することで、信頼性を強化。
一方で、整合不足が引き起こす課題
① プロトコル非互換
OB v3はVC形式であってもOID4VPに非対応です。いわゆるDID/VCにおける、Issuer/Holder/Verifierのようなステークホルダーの座組でクレデンシャルの授受を行うためのプロトコルに完全準拠している訳ではありません。つまりウォレットからOBを提示するとしてどうするの?という問題がございます。
OID4VPとはVCが検証者に対して提示される際に、どのような方式に従ってデータの授受が行われているのかを定める重要なプロトコルです。同じプロトコルに乗っ取りデータの授受が行われることで、どんなウォレットでも検証者は共通の認識を元にクレデンシャルの提示を受けることができます。OBの仕様書ではこれに対する準拠は明確にされている訳ではなく、データモデルとしての互換性を持っているくらいの記載となっています。
② VCモデルとの違い
実際にOB v3の定義を見ていくと、個々のプロパティなどはVCモデルを拡張している形になっています。ベースとしては元々定義されていたデータモデルを使いながらも、独自にデータを持たせたりしているような形になっています。ウォレットはOB v3におけるデータの形と、純粋なVCにおけるデータの形を見分けるシーンも出てくるかと思います。となると、OB v3はVCだ!というのは非常にざっくりとした見方になっていて、実際は似て非なるという捉え方をしておいた方が色々とコミュニケーション齟齬が起きないかと思います。
③ v2資産との後方互換性
OB v3はv2とは互換性がないと、仕様書にガッツリ記載されています。v2をVCとしてどのように読み替えるのか?という以前に、そもそもモノとして完全に違うものということですね。既存バッジは再発行が必要で、発行者に負担が発生します。
過去に発行したv2のバッジをウォレットに格納可能なVCとして派生的に発行するような施策についての文献もございます。これはv2で発行したOBをVCに埋め込み(おそらくEvidenceとかで持っている?)をして新たにVCとして発行してウォレットに格納、VPとして提示するというような実証を行っています。
理想と現実のギャップ
| 項目 | 理想 | 現実 |
|---|---|---|
| 相互運用性 | DID/VC準拠でSSIウォレットやOID4VCと接続 | データ構造のみVC、プロトコルは中央集権型 |
| プロトコル | OID4VCI/OID4VPで即時発行・提示 | IMS独自モデル |
| 後方互換性 | v2資産を容易に移行 | 直接互換なし、変換必要 |
まとめ
Open Badges v3は形式上VCになったことで国際的な相互運用性の可能性を開きましたが、現状はIMS独自のエコシステムに依存しています。しかし、OID4VC対応やDID活用などの技術的強化により、教育分野を超えたデジタル証明の共通基盤として発展する余地があり、今後も弊社としても技術面でのサポートにまい進して参りたいと思います。
参考文献