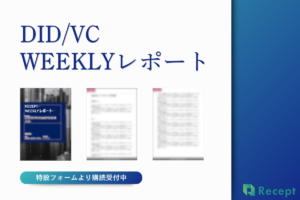【Web5とは?】インターネットの進化の歴史
本日は、Web5というまたまたポップな話題について触れようと思います。
しかし、分散型!ブロックチェーン!という感じではなく、もっと言えばブロックチェーンとは切り離された技術スタックを使うこともできるという思想になっております。
ニュース原文:
インターネットによって私たちの生活は大きく変化してきました。
Web5という思想を理解する上で、まずはインターネットの歴史を振り返ろうと思います。
Web1:インターネットの黎明期
Web1は、読み取り専用の時代でした。
情報を閲覧することはできましたが、ユーザー同士のインタラクションやコメント機能などは存在しませんでした。
「デジタル図書館」のようなものだったと例えられています。
- 主にHTMLで構成されたテキスト主体のウェブサイトが中心
- 情報提供者はごく少数で、ユーザーはただの受動的な読者ほとんど
Web2:インタラクティブな共有時代
FacebookやYouTube、Twitterなどのプラットフォームが中心となり、ユーザーは情報を消費するだけでなく、積極的にコンテンツを作り出すようになりました。
以下のようにファクトが紹介されています。
- ソーシャルメディアの普及で、アイデアやクリエイティブな活動
- しかし、大手プラットフォームがデータを掌握し、ユーザーの活動から利益を得る構造に。楽しさの裏で、実際に得をしていたのはユーザーではなくプラットフォーム。
実際に得をしていたのはユーザーではなくプラットフォームでした。
こちらに関してはWeb5のポジショントークも多分に含まれるかと思いますが、とはいえ、個人情報の流出や新たな犯罪(闇バイトなど)のように、
便利になったことによる新たな課題が生じていることは事実かと思います。
Web3:所有権の復活
そんなWeb2に対する解決策として、Web3が誕生しました。
Web3はブロックチェーン技術を基盤とし、分散化の理念を掲げて登場しました。
デジタル資産やデータをユーザーが所有できるインターネットを目指し、暗号通貨やNFT、DAO(分散型自律組織)などの新しい概念が注目を集めました。
- 一般ユーザーにとって技術的なハードルが高く、実用性が限られる場面も
- 高額なトランザクション手数料や遅延が問題となり、投機目的の利用が主流に
ニュースの本文では、Ownership, but at a Costと紹介されており、代償が伴うとされています。
こちらに関しても当然Web5思想によるバイアスはかかっていて、そもそも実用性を出さないといけないのか?という話もございます。
要はNFTが貰えて、好きなキャラクターのアイコンの所有権があったらなんか嬉しい!みたいな価値の感じ方もあるのでは、と個人的には考えております。
Web5:成熟したインターネットの到来
そして、Web5が登場します。
Jack Dorseyが率いるTBDが提唱するのがWeb5という概念です。
この新しいインターネットは、Web2とWeb3が抱える課題を解決し、ユーザーに焦点を戻すことを目的としています。
2 + 3 = 5 ということで、Web5と言われています。
- 中核にあるのは「自己主権型アイデンティティ」。データやアイデンティティの管理を企業やブロックチェーンではなく、ユーザー自身が担う。
- Web5は、分散型識別子(DIDs)や検証可能な資格証明書(Verifiable Credentials)といった技術を活用しながらも、ブロックチェーンに過度に依存しない。
ということで、Web3というある種ユーザービリティに課題があったものを解決しながらも、ユーザーのデータやアイデンティティを自己主権に戻していくという考え方です。
DID/VCという技術を取り扱う筆者としてもこのWeb5という考え方に共感もしています。
同時に、自己主権型アイデンティティそのものがWeb3と同じようにユーザービリティが良いのか?であったり、顧客にどのように価値提供するのか?
は依然課題として残っている部分でもあるかと思います。
もちろん価値提供できることに自信はございますが。
まとめ
ということで、(あんまりいいニュースがなくて)Web5というポップな単語について触れてみました。
Web2 + Web3 = Web5 と覚えてください!
★特別なお知らせ★
デジタルアイデンティティの最新トレンドを毎週お届け!
業界の最前線をまとめた「DID/VC Weeklyレポート」を毎週無料で配信中です。こちらから簡単に登録できますので、ぜひ情報収集や新規事業のタネ探しにご活用ください。